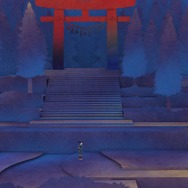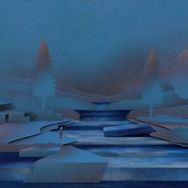【TGS 2012】Youtubeの動画を見てひらめいた・・・『TENGAMI』開発者特別インタビュー
盛況のうちに終了した今年のセンスオブワンダーナイト(SOWN)。中でもトリをつとめた『TENGAMI』は、「飛び出す絵本」的な世界で繰り広げられる和風アドベンチャーで、会場に多くの驚きを与えました。
その他
全般

本作を作ったNyamyam(ニャムヤム)「http://nyamyam.com/」は、イギリス人のフィル・トッセル氏、ドイツ人のジェニファー・シュナイダーライト氏、そして鬼縄在住の日本人、東江亮氏の国際ユニットです。SOWNにあわせて来日したお二人に、開発体制やゲームデザイン、さらにはインディゲーム開発者としてのマインドまで、幅広くインタビューを行いました。
―――はじめにお二人の経歴を教えてもらえますか?
フィル:僕は1996年に大学を卒業すると、すぐにレアに就職して、ずっとプログラマーとして働いてきた。最初に参加したのが『ディディーコングレーシング』(N64)で、『スターフォックスアドベンチャー』(ゲームキューブ)、『カメオ:エレメンツ オブ パワー』(Xbox 360)ではメインプログラマーを務めたんだ。レアで手がけた最後のタイトルは『キネクトスポーツ』で、その頃はゲームプレイ・ディレクターになっていた。それが終わった2010年に退社して、二人でニャムヤムを起業したんだ。
―――日本でも人気の高いゲームばかりで、驚きました
ジェニファー:私は大学ではコンピュータサイエンスを勉強したの。卒業して来日し、2005年にアクワイアに入社して、プログラマーとして『忍道 焔』(PSP)と『侍道3』(PS3・Xbox360)の開発に参加したわ。でも、日本以外でのゲーム開発も経験したくて、2009年にアクワイアを退社してイギリスに移住し、レアに入社したの。その頃は半分プログラマーで、半分ゲームデザイナーという感じだったかな。そこで『キネクトスポーツ』の開発チームに入ったの。フィルと知り合ったのは、その頃ね。そしてニャムヤムを設立したの。
―――日本でも働かれていたんですか。驚きました。言葉は大変ではなかったですか?
ジェニファー:最初は英語で会話していたけど、だんだん日本語でもコミュニケーションできるようになったわ。それに当時は、プログラム言語が「第3の言語」だったから。
―――なるほど。会社の「ニャムヤム」ってどういう意味ですか?
ジェニファー:特にたいした意味はなくて。ほら、日本には「ピコピコ」とか、いろんな擬音があって、それぞれイメージがあるでしょう? ニャムヤムも音のイメージで決めました。可愛さとか、楽しさとか、美味しいとか、そんな感じね。
―――ニャムヤムはバーミンガムにスタジオがありますが、沖縄から東江亮(リオ)さんもプロジェクトに参加していますよね?
ジェニファー:リオも10年くらいレアでアーティストとして働いていたの。『パーフェクトダーク ゼロ』(Xbox 360)や、Xbox LIVEのアバター制作などを手がけていて、親交があったわ。でも結婚して、子どもが産まれたりと、生活環境が変わって。それで半年前に会社を退職して、実家のある沖縄に戻ったの。それで、こちらから誘って。ちょうど良いタイミングで「テンガミ」に参加してくれたわ。
―――ふだんのコミュニケーションはインターネットですか?
ジェニファー:メールとか、スカイプとか。毎日日本時間で朝の8時にスカイプでミーティングをして、進捗を確認したり、次に何を作るか決めたりしているの。データのやりとりはDropboxね。すごく良い感じで進められているわ。
―――でも、直接顔をあわせてのコミュニケーションも重要でしょう。
フィル:実は今回の東京ゲームショウで、久しぶりに顔を会わせたんだ。でも普段の仕事で、特別フラストレーションを感じたことはないよ。人数が少ないから、言った、言わないのコミュニケーションギャップも生まれにくいしね。
―――役割分担はどうなっていますか?
フィル:僕もジェニファーも、二人ともゲームプログラマーであり、ゲームデザイナーであり、ディレクターなんだ。つまり、みんなで考えてみんなで作るってこと。リオはアーティストだけど、いろんなゲームのアイディアを出してくれる。だから三人とも名刺には「ゲームクリエイター」という役職にしているんだ。
―――懐かしいですね。8ビット時代のゲーム開発を思い出させます。少人数でゲーム開発ができるインディならではですね。
フィル:ゲーム開発を「再創造」したいんだ。僕はNintendo64でゲーム作りを始めた。チームはまだ小さかったし、みんなで話し合いながら作ることができた。でも、そのうち開発チームが大きくなって、僕はただのプログラマーになってしまった。もっと、いろんなことに首を突っ込みたかったんだ。
ジェニファー:ゲーム業界に入りたい人は、みんなゲームを作りたいはずよ。今は自分の役割しか担当できない。みんなパーツしか作れない。「ゲーム作り」ができなくなっているのよ。ニャムヤムでは、もっと昔のようなゲーム作りをしたい。それがプログラマーでもゲームデザイナーでもアーティストでもなく、「ゲームクリエイター」と名乗っている理由なの。だって、みんなゲームを作ってるんだから。
■できるだけゲームメカニクスをシンプルに保ちたい
―――今年の「センスオブワンダーナイト」入選作となった『テンガミ』ですが、どこからアイディアが生まれたのですか?
フィル:実はずいぶん前にYoutubeで「飛び出す絵本」のCGムービーを見ていて、元となるアイディアを閃いたんだ。そこから、ずっと温めていたんだ。
ジェニファー:でも、その当時はまだ、どうやったらゲームになるか、見当もつかなかったの。それがiPadのようなタブレットが普及して、だんだんとイメージが固まってきたわ。「飛び出す絵本」の世界で、絵本を読むように、ゆったり進むアドベンチャーゲームはどうだろうって。
―――たしかに、タブレットの「めくる」操作は、このゲームにすごく向いていますね。
フィル:初代iPadの発表を見て、これで何かゲームを作りたいと思ったんだ。それで、はたと気がついた。これは「飛び出す絵本」アドベンチャーに最適なプラットフォームだって。でも、実際にデモ版を作り始めてからも、試行錯誤が続いて、気がついたら1年たっちゃったんだけど。
―――途中でギブアップしようと思いませんでしたか? お金の問題もあるし。
ジェニファー:実際、とても怖かったわ。最初は実際に「飛び出す絵本」を買ってきて、分解するところから始めたの。でも1年くらい、いろいろ試行錯誤した結果、いろんなプロトタイプがiPadで作れるようになったわ。それで「飛び出す絵本」スタイルのアドベンチャーは、タブレットに最適だとわかったの。
―――イギリスの書店には『ピーターパン』『ふしぎの国のアリス』などの絵本もあったかと思いますが、なぜ和風の世界観を選んだんですか?
フィル:僕ら全員が日本とかかわりがあるから。リオは日本人だし、ジェニファーは日本で4年間、働いたことがある。僕も日本に10年前に初めて来て、それから何度も旅行したことがある。日本のテレビゲームやマンガ、アニメも大好きだしね。それだけじゃなくて、古い建造物や歴史、それから和紙にも興味があった。
ジェニファー:それに「飛び出す絵本」と和紙の組み合わせは、とてもおもしろいと思ったの。日本には和紙や千代紙など、西洋とは違う紙の文化があるわ。それでプロトタイプを作って、これはいけそうだとなった時、アートスタイルに和紙のテイストを応用することを思いついたの。こんな風に日本文化からインスパイアされた部分がたくさんあるわ。
―――和紙で作られた「飛び出す絵本」はいろんな意味で難しいので、和紙テイストのデジタル版「飛び出す絵本」はとても挑戦的です。特にアートスタイルの面で、グラデーションがすごくいいですね。グラフィックアセットをどうやって作っているのですか?
フィル:和紙をデジタルカメラで撮影して、テクスチャーに使ってるんだけど、このアートスタイルを作り上げるまで、すごく時間がかかったよ。リオが日本にいてくれて本当にラッキーだったね。和紙を使うにしても、実際にどうやってゲームに落とし込んだら良いか、わからなかった。いろんなやり方をためしたよ。レベルデザインをするのに、実際に紙で「飛び出す絵本」を作ってみて、そこに裁断した和紙を張ってみたりもした。
ジェニファー:そこで「飛び出し」のメカニズムを検証して、実際にDCCツールで背景を作っていったんだけど、そこでも試行錯誤だったわ。デモ版では背景が草なら草らしく、縁がぎざぎざになっているけど、最初はもっとラフなパーツを作って、試してみたの。そうやってある程度イメージを固めておいて、そこからリオが完成形のパーツに仕上げていったのよ。和紙の撮影や色味の修正、必要なポリゴンデータの作成、テクスチャーの貼り付けなどは、すべてリオがやってくれたわ。
―――ゲームメカニクスがすごくストイックですが、これは意図されていますか?
フィル:できるだけシンプルに保ちたいんだ。実際、このゲームには3つのメカニクスしかない。歩くこと、ページをめくること、それから画面をスワイプして、仕掛けを動かすことだ。すべてのパズルはこの3つの要素で構成されている。主人公が戦ったり、死んだりすることもない。
―――シンプルに保つことは、とても難しいですね。
フィル:そのとおり。ごちゃごちゃ、付け加えていくことは簡単さ。たいていのゲームは作り始めはシンプルでも、いろんな理由で複雑になっていく。特に商業ゲームはその傾向が強い。でも、そうはしたくなかったんだ。
―――サウンドもすごくいいですね。伝統的なオーケストレーションサウンドが、このゲームの世界観と良くあっています。
フィル:ありがとう。レア時代に一緒に働いていて、2年前にフリーランスのゲーム作曲家になった知り合いに頼んだんだ。『スーパードンキーコング』シリーズの音楽などを手がけていて、すごく有名な作曲家だよ。とてもラッキーだった。
―――背景ストーリーなどはありますか? なぜ主人公は一人なのでしょう?
ジェニファー:私たちは古典的なゲームのストーリーを持ち込むつもりはないの。遊んでくれた人それぞれが、自由に想像してくれれば良いなって。
フィル:もっと詩的な体験ができるゲームにしたいんだ。
■『TENGAMI』は外国人だからできたゲーム
―――では、もっとキャラクターが登場するなどのビジョンはありますか? また日本は美しい四季で知られていますが、季節感をもっと取り入れるなどは?
フィル:それはもちろんだよ。センスオブワンダーナイトでも説明したとおり、まだ20%の完成度なんだけど、もっとステージ数を増やして、さまざまなキャラクターや、四季おりおりの情景を取り込みたいと思っている。
―――デモ版でも伊勢神宮をモチーフにした建造物が登場しますが、沖縄を舞台にしたステージはどうですか? リオも住んでいます。
フィル:それはいいアイディアかもしれないね。 沖縄県は日本本土とは違う文化があるし。でも、まだ行ったことがないんだ。
―――僕もそうです(笑)。ちなみにセンスオブワンダーナイトの後で、ある日本人のゲーム開発者から「ホントは日本人である僕らが、ああいったゲームを作るべきなのに、恥ずかしい」といったコメントが聞かれました。
ジェニファー:でも、自分たちの文化をゲームにして、それで世界の人に理解してもらうって、実はとても難しいと思うわ。 実際に暮らして、細かいところまで知りすぎているから。『TENGAMI』にしても、私はドイツ人だし、フィルはイギリス人で、アウトサイダー。もちろん、私は日本に住んでいたから、他の外国人よりも深く日本文化を説明できる。でも、外国人だから作れているところはあると思うわ。
フィル:外国に旅行すると、みんな珍しいから、写真をよくとるよね。でも、そこに暮らしている人は、そうでもない。僕にしてもイギリスは故郷で、よく知っているだけに、ほとんどの風景は退屈さ。
ジェニファー:私もそう。ドイツの風景を見ても、なんとも思わないもの。でも日本から来た観光客は、ドイツが美しい国だって言ってくれる。それと同じね。
―――日本ではどんな場所を旅行しましたか?
フィル:神社仏閣とか、歴史的な建造物とか・・・。伊勢神宮にも行ったことがあるよ。伝統的な建造物が大好きで、たくさん写真を撮った。
ジェニファー:私も伊勢には行ったことがあるわ。でも京都や鎌倉の方が多いわね。江ノ島はとてもキュートで、大好きな場所よ。
―――これはハードコア向けのアクションゲームではありませんよね。かといってカジュアルゲーマー向けのアドベンチャーゲームというわけでもなさそうです。
ジェニファー:ええ。なにか、もっと落ち着いて、ゆったりとしたゲーム体験がしたかったり、異世界への旅を体験してみたかったり・・・。説明するのが難しいけど、少なくとも「カジュアルゲーマー」ではないわ。
―――とても先進的だけど、マーケティングが難しいですよね。もっとも、それこそがインディゲームなんだと思います。
ジェニファー:そのとおりね。
―――完成したら、自分たちでパブリッシュされますよね。
フィル:もちろん。来年中に完成させて、販売したいと思っているよ。
―――インディゲームフェスティバルなどに挑戦されますか?
ジェニファー:もちろん。直近では米ロサンゼルスで10月4日から7日まで開催されるINDIE CADE2012に出展するわ。
■実は日本よりイギリスの開発文化の方がクール?
―――フィルさんはずっと英国暮らしですが、ジェニファーさんは日本からイギリスと、転職の度に働く国も変わってますよね。しかも故郷のドイツで働いたことがない。
ジェニファー:そういえば、そうね(笑)
―――日本でも多くのゲーム開発者が転職しますが、ほとんどは日本、それも首都圏に留まっています。とても興味深い働き方に見えます。
ジェニファー:ドイツで生まれ育って、長い間すごしたけど、もっと大きな世界を見てみたくなったの。それも国の違いだけじゃなくて、ライフスタイルの違いについても、知りたくなったのね。たとえば、ある国では長いバカンスをとるけど、そうでない国もあるでしょう。そのためには、別の国で実際に働くのが一番だと思ったの。それに、ドイツに戻りたくないという気持ちもあったわ。
―――ただ、別の国で働くことは、楽しいことだけではないと思います。たとえば日本での生活はどうでしたか?
ジェニファー:もちろん、コミュニケーションで困ることもあったけど、仕事ではプログラミングが役にたったわ。これがゲームデザイナーだったら、難しかったかもしれないわね。というのもゲームデザイナーの仕事には文化的な要素が大きいと思う。子どもの頃から親しんできたマンガやアニメといった、共通言語の多さが求められるから。
それにみんな、すごく良くしてくれたわ。ただ働くだけじゃなくて、チームがコミュニティみたいだった。むしろイギリスの方が、ちょっと大変だったかもしれないわね。
―――あれ、そうなんですか?
ジェニファー:たとえば東京だと、仕事が終わった後に飲み会をするとか、よくあるわよね。でもレアではそういうことが、ほとんどなかったの。実際、チームで飲み会に行ったりすることは、一度もなかったわ。チームの連帯感という意味では、日本の方がずっと感じられた。
―――でも、イギリスにはパブがたくさんあるでしょう?
フィル:ただ、レアは郊外あるから、みんな車で通勤するんだ。だから仕事帰りに、みんなでパブによって一杯、なんてことが難しいんだよ。仕事が終わったら、みんな家に帰っちゃう。そこから近所のパブに行くんだ。仕事でのつきあいと、プライベートのつきあいが分かれているんだ。
―――なるほど、車社会という意味では、日本の田舎もイギリスと似ているかもしれません。一つの国でも様々な働き方がありますし、それぞれの違いはおもしろいですね。
ジェニファー:そのとおりね。
■もっと開発者同士でコミュニケーションを深めよう!
―――それでは最後に、日本のインディゲーム開発者にコメントをいただけますか? ご存じの通り日本ではインディゲーム開発者が非常に少ないのが実情ですが、そうした働き方に興味のある開発者は少なくありません。
ジェニファー:もし興味があるなら、みんなインディゲームになることをオススメするわ。そうしたら、少なくとも自分が本当に作りたいゲームが作れるようになるし、ストレスも激減するから。もちろん、お金の問題は大切だし、ある程度の蓄えが必要だけど、もし途中でお金がなくなったら、また就職すれば良いのよ。まず貯金して、それからインディゲームの世界に飛び込みましょう。
フィル:日本でもゲーム会社でストレスをためている人が多いと思うけど、僕もかつてはそうだったから、その気持ちが凄く良くわかる。最後の方は自分では何も決められなくなっていて、ただ周りの進捗状況を確認して回るだけの日々で、限界だったんだ。それが会社を辞めたら、一気にストレスがなくなった。もちろん、お金のことはちょっと怖かったけど、ライフスタイルが劇的に変わったよ。
―――僕も昔は出版社に勤めていて、フリーランスになったので、よくわかります。
フィル:実際、日本のゲーム作りに関する創造力はすごいと思う。僕は子どもの頃から日本のゲームで育ったし、もっと多くの人にインディゲームの世界に挑戦して欲しい。西洋でも多くのゲーム開発者が、そう望んでいるよ。そうなれば、もっとエキサイティングなことがおきると思う。
ジェニファー:ひとつ問題があるとすれば、でもホントに些細な問題だと思うけど、日本人が英語を喋らないことね。それが自分たちの作るゲームを世界のユーザーに届けるうえで障害になっていると思う。日本のゲーム市場は世界の中では小さいし、国際的なゲーム開発者のコミュニティに飛び込んでいけば、自分たちのゲームを世界の人に遊んでもらえる機会も増えると思うわ。もっと多くの人とコラボレーションすることが大切だし、そのためには英語でコミュニケーションしないとね。
フィル:その意味でも僕らは、イギリス人とドイツ人と日本人のコラボレーションができていて、すごくラッキーだと思う。大切なのは文化的な交流をすること。最近は日本のパブリッシャーも海外のディベロッパーと仕事をするようになっているけど、必ずしも全てが成功しているわけじゃない。それよりも、まずはゲーム開発者同士で、コミュニケーションを深めていくことが大事だと思う。そうすれば、もっとおもしろいゲームが作れるようになるよ。
ジェニファー:とりあえず、みんなでパスポートをとりましょう。そしてINDIE CADEのようなイベントに参加して、一緒に盛り上がりましょう。インディ開発者の友達を作ったり、交流を深めるには、それが一番よ。
―――ありがとうございました。
《小野憲史》
この記事の写真
/