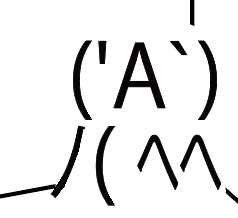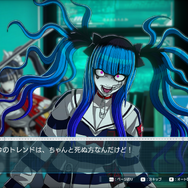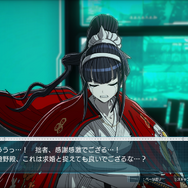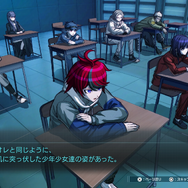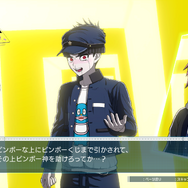2025年4月24日発売予定の『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』(以下、HUNDRED LINE)。『ダンガンロンパ』シリーズの小高和剛氏、『極限脱出』シリーズの打越鋼太郎氏がタッグを組んでシナリオ制作にあたるということもあり、両氏のファンからも大いに期待を集めるシミュレーションRPGです。
そんな本作は、小高氏が代表を務めるTookyo Games初となる新規IP作品でもあります。“狂”の字を掲げる会社が放つ最新作として、さまざまな期待を背負った『HUNDRED LINE』がどのようにして生み出されてきたのか、そしてこの作品ならではな独自性とはなんなのか――小高氏と打越氏に直接お話を聞きました。
※本稿では、体験版以降の展開に関するネタバレが含まれます。

◆どこかしら「狂ってる」と思わせる特徴がないと勝負できない
――まずは、おふたりの自己紹介からお願いできますでしょうか。
小高Tookyo Gamesの小高和剛です。『HUNDRED LINE』ではディレクターとシナリオを担当しています。
打越同じく、Tookyo Gamesの打越鋼太郎です。『HUNDRED LINE』では“ハンドレッドルートシナリオディレクター”を担当しています。
――ありがとうございます。まずは本作が開発にいたるまでの経緯をお伺いできればと。
小高スタートは2020年ぐらいでしょうか。僕がシナリオを書き始めて、それからどんどん皆にも入ってもらって、メディア・ビジョンさんにも声をかけて。初の自社IPということもあったので最初はTookyo Gamesだけでやるつもりでしたが、資金的にも厳しくなってきたので、パブリッシャーとしてANIPLEXさんと組むことになりました。

――最初のころはもう少し規模が小さくなる予定だったのでしょうか。インディーゲームみたいな。
小高そうですね。スタートしていたときは必要最低限に抑えるべきか迷っていたんですけど、進めていくうちに「これはインディー的な予算だと、逆にしょぼくなってしまうかも」と思ったんです。なのでここはもうフルスロットルでいくしかないと思い、パブリッシャーさんを探す方向に舵を切りました。
――なるほど。最初は小高さんだけというお話でしたが、打越さんが加入されたのはどのぐらいのタイミングだったのでしょう。
打越だいたい半年後ぐらいでしょうか。

小高打越さんには「100エンド作りたい」ということだけを伝えて、そこから元となるシナリオと大きく分岐する箇所を僕のほうで書いて、それをお渡しして最終的に100個まで分岐させていくところから取りかかってもらった形ですね。
――……とんでもない無茶ぶりにも思えますが、打越さんは最初聞いたとき、どう思われましたか?
打越最初聞いたときは、とにかくバッドエンドをいっぱい作ればいいのかなと思ったんです。でもよくよく聞いてみるとそうじゃなくて、「全部が本編で、全部が真ルートと呼べるようなものにしてほしい」と。「頭おかしいんじゃないのか」って思いました。
いったんフローチャート形式で簡単な出来事を書きだしたんですけど、その量も膨大で。それを見せて「あなたが言っていることはこういうことですけど、本当にやるんですか?」って聞いたら「そうだ」と。
小高分岐するうえで、話のジャンルすら変わってほしいなっていうのが今回のコンセプトでした。
最初は内部で『100日戦争』って呼んでいたんですよ。なんで100日にしたかは覚えてないんですけど、「50日って言うよりかは100日にしたほうが強そうだよな」とか、そういう感じだったんじゃないかと。で、100日なら100分岐にしたほうがいいんじゃない? ってなりまして。
――すごい、この時点で正気じゃない気がしています。
小高まあ、ずいぶん前の話なので正確な経緯は覚えてないですけどね(笑)。でも新規IPを作るのであれば、どこかしら「狂ってる」と思わせる特徴がないと勝負できないと思っていたんです。Tookyo Gamesにはシナリオライターもたくさんいますし、イラストレーターもいますから、今回のような多数の分岐と大量の素材で勝負するべきかなと。

――作る体制は揃っていたからこそ、という感じなんですね。ただ話を聞いていると、100エンドと決めた時点でボリュームがすごいことになっていそうですが、実際にパブリッシャーさんを探し始めたタイミングってどれぐらいの時期だったんでしょう。
小高それは100エンドを決めた段階よりずっと後ですね。
でも、もしなにも作っていない状況でこのゲームの企画書を書いても、多分どのパブリッシャーさんにも通らないんですよ。僕らはシミュレーションRPG自体を作ったことがないし、そのうえで100エンドなんてできるはずがないというか。それこそ打越のリアクション通り、「おかしい」って言われるだけだと思います。
――だとしても初のIPとしてはやる必要があったし、曲げられない部分だったと。
小高そうですね。こういう狂ったことじゃないと意味がないっていうか、そもそも勝負できないと思っていたので。
本当に製作費が足りなくなったタイミングで、パブリッシャーを見つけるのか、あるいはプロローグだけ売るような形で小分けにして販売するのか、という話になったんです。でも「小分けにするのは日和ってるんじゃないか」っていう話になって、最終的にパブリッシャーを見つける方向で話が進んでいきました。
――最後まで「狂っている」という武器を持つことをやめなかったんですね。ではそんな本作のタイトルに込められた意味についてもお伺いできれば。
小高正式にタイトルを決めることになって、そこで誰かが出した案でした。物語にハンドレッド(100)のラインがあるし、ハンドとレッドで“血塗られた手”みたいになるし、いいんじゃないかなと。あとは『最終防衛学園』っていうのがキャッチーで、学園ものだというのがわかりやすいなと思ったので、副題に入れました。
――なるほど。学園ものってすぐわかりますし。
小高まあそうしたことで、結果的にX(旧Twitter)でどう呟いていいかわかんなくなっちゃったんですが(笑)。公式の略称である『ハンドラ』って言ってくれる人もいれば『最終防衛学園』って言う人もいるし、みたいな。
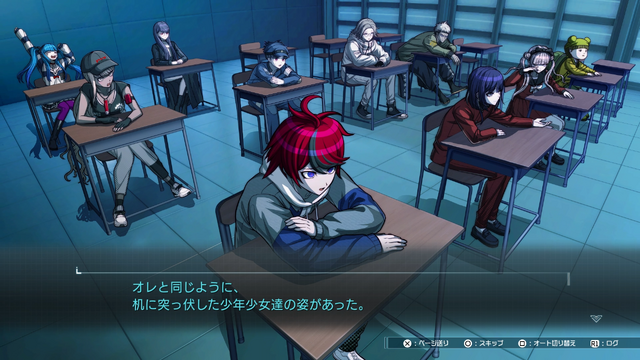
◆シナリオライターがスクリプトも担当。アドベンチャーパートは細かな演出に注目
――プレイしていても感じたのですが、やはりアドベンチャーパートの作りは流石というか、情報の出しかたが絶妙でした。
小高やっぱりゲームのやめ時を無くすっていうのは常日頃から思っているところでして。プロットの段階でも小さな事件をたくさん羅列して、それを各所に捻じ込んだような形ですね。100日を引っ張らなきゃいけないというのもあったので、絶対に何かが気になった状態で1日を終わってもらおうという意識はありました。
――実際ゲーム内でも100日までかなりかかった覚えがあります。イベントも盛りだくさんでしたし。
小高100の分岐はありますが、だとしても1周やるだけでもおなかいっぱいになるぐらいまでは詰め込まないと。やっぱり狂ってないじゃないですか。
――なるほど。クリアまでプレイした身としては、間違いなく狂っていたと思います(笑)。演出もかなり凝っていましたが、好きな演出などはありますか?
打越僕は説得パートですかね。あのバージョンに至るまでにいろいろとあったので。

――そうだったんですか?
小高なんなら一瞬諦めかけたパートでもあるんですよ。「あまりよくはないけど、もうしょうがないのかな……」って。
打越ああいった演出面は、シナリオができてから詰めていった部分なんです。なかでも説得パートはミニゲームっぽい、あまりメインではない部分なので、どうしてもクオリティアップが後回しになってしまい……。
――そうなんですね。プレイしていてかなり楽しいパートだったので意外でした。
小高けっこう危機感がありましたね。「どうしよう、全然面白くないぞ」って。
打越そうそう。僕らはもう「しょうがないじゃん」って感じだったんですけど、下から「これじゃダメでしょ」って言われて。それもひとりふたりじゃなく、もっといろんな人から(笑)。そのおかげでクオリティアップできた箇所なので印象に残っていますね。
――ボトムアップというか、現場からの突き上げというか。そういう熱意でできたパートだったわけですね。小高さんはどうでしょう。
小高僕的にはですね、今回はシナリオを担当したライターが直接スクリプトをやっています。なので全体的にシナリオに即した表情や音楽、ボイスになっているところに注目してほしいです。
アドベンチャーゲームだと多いのですが、こういうRPGではまず無いと思うんです。かなり細やかな演出になっていると思います。

――なるほど! シナリオライターが書いた通りの表情、演出がそのまま出力されているわけですね。
小高そうですね。あとはジェットスタジオさん制作のムービーパートもかなり力を入れているので、そこも楽しんでいただければ。『ダンガンロンパ』から『超探偵事件簿 レインコード』までずっといっしょにやってきた方々で、僕らの作風もよくわかってくれています。
――最初のオープニングも長いですよね。昨今のトレンドだと短くして、まずはプレイさせるようなものが多い印象ですが。
小高そこはもう、あえてやった部分です。ふつうだったらもっとプレイできるようになるのが速いと思うんですけど、最近そういうのが多くなってきているなと思って。逆にもう、『FINAL FANTASY VII』とか『FINAL FANTASY IX』みたいな、“ムービーゲー”って言われていたような時代まで戻っていいんじゃないかと。
――時代に対する反抗精神みたいなものがあったわけですね。
小高そうですね。それに、ぼくらはゲームだけじゃなくアニメや漫画原作もやっていたりするので、そういうTookyo Gamesの集大成として「オープニングはもうアニメーションにしよう」ということもかなり初期のほうから決めていました。
それと、オープニングの場面は唯一の日常生活パートなので、ゲームのフィールドを作るよりかは、ああいう見せ方にしたほうがコスト的にもよかったんです。
――なるほど。制作するうえでも合理的なやりかただったわけですね。

小高(打越氏のほうを見つつ)演出だと、あとあれだよね。イベント絵が大変だったよね。
打越イベント絵は……600点以上あったなあ。
小高絵コンテとか字コンテとか、チェックが大変すぎて。
――ろ、600以上……。ハンドレッドルートとかはとくに監修が大変だったのでは。
打越そこは流石に全部見てられないので、基本的にはライターさんたちに監修をお願いしていましたね。
小高でもデバック時とかにボロボロ出てくるんだよね(笑)。「ここは学生鎧(クラスアーマー)じゃないじゃないでしょうか」とか。
打越「なぜか急に私服になってますけど」とか(笑)。言われて頭を抱えるんですよね。

――ちなみにライターさんって、どれぐらいの数が関わられているのでしょうか。
小高11名ですね。僕らを抜いて9名。
打越……本当はもっといたんですけどね。
小高そうね。途中で屍になった人がちらほらといました(笑)。
――なるほど。小高さんがメインとなるシナリオを書いて、ハンドレッドルートの100エンドを打越さん含め10名で書いていった感じなんですね。
小高基本的にはそうなりますね。ただ、結果的に最後のほうに誰も担当できていないルートとかもあったので、そういうものは僕が書いています。最初は一切やらないつもりだったんですが、「実装を諦めるか、お前が書くか」みたいな雰囲気になってて(笑)。よっしゃ、やるかと。
――本作の目玉でもありますもんね。
小高そうですね。諦めきれなかったです。
◆表情差分は3000以上。こだわりと狂気で走りぬいた5年間の結実
――戦闘についてもお話を聞ければと思うのですが、まずシミュレーションゲームに挑戦した理由ってあったりするのでしょうか。
小高これはもう、全員が同時に戦う姿を見せたかったからですね。15人全員が必死に、同時に戦うのであれば、もうシミュレーションゲームしかないだろうと。
打越それを聞いて思い出したけど、最初ボツになったときはタッチして交代するタイプのアクションゲームだったよね。
小高そうだね。
打越そのときは全員で防衛するって言っているのに、なぜかひとりずつ戦っているような絵面になっていまして……やっぱりシナリオ的にもしっくりはこなかったんですよ。だから本当に、シミュレーションゲームにしてよかったなと思います。
小高むしろほかのジャンルだと合わないというか。自分が使うキャラクター以外はNPCに任せるという案もあったのですが、これだけ個性的なキャラクターが沢山いるのなら、やっぱり自分で動かせたほうが楽しいだろうと思ったんです。

――シミュレーションがやりたいというより、コンセプト通りにやるならシミュレーションだろう、と。
小高そうですね。あとは最初から組むと決めていたメディア・ビジョンさん自身、とてもシミュレーションRPGを作るのが得意なので、そういう意味でも親和性があるんじゃないかと思いました。
――バトルの制作はどういう感じで進められたのでしょうか。
小高まず僕が「こういうプレイ体験を味わわせたい」とか「こういうボスが出てきます」みたいな、シナリオで言及している部分をすべてメモのような形で書きだして、それを元にメディア・ビジョンさんのほうで作ってもらいました。
――シミュレーションバトルだけど命が軽い、みたいな。
小高死んでは生き返るのをくり返す、とかもそうですね。そこから僕が見たのはシナリオの内容に即しているかどうかぐらいで、ゲーム性の面白さはメディア・ビジョンさんと、途中からプロジェクトに参加した元アトラスの登川がしっかりと底上げしてくれました。

――なるほど。少し気になったのですが、シミュレーションRPGなのに死を許容する……というかむしろ推奨するようなゲーム性はかなり独特なものだと思うのですが、そのアイディアはいつごろからあったのでしょう。
小高最初からですね。シミュレーションRPGって後半の展開が極端になりがちというか、優勢になったら楽勝だし、劣勢になったら覆すのは難しいし……そういうのはなんとなく嫌で、「逆転が起こりやすいシステムにしてほしい」というのを最初の方に伝えていたんです。そこから「味方が死んだら必殺我駆力(必殺技)のゲージが溜まるようにしたらいいんじゃないか」という案をメディア・ビジョンさんから出していただきました。



――たしかにプレイ中、劣勢の状態から巻き返すような場面は何度もありました。でもやっぱり、かなりぶっ飛んだシステムですよね。
打越僕も聞いたときは同じ感想でした。意味わかんなくて(笑)。明らかにセオリー通りじゃないんですよ。「ヒットポイントが1になったら撤退とかでいいじゃん」って思ってました。
でも実際プレイしてみたら、ちゃんとその面白さに気付けるんですよね。それによくよく考えてみると、『HUNDRED LINE』が持つ物語のテーマともすごく合っている。「なるほど、そういうことがやりたかったのか」と感心しました
――奇抜だけど、奇抜なだけじゃない。ちゃんと理にかなったものになっていますよね。あとバトルについてだと、かなりキャラクターごとに個性が違いますよね。バランスを取るのは大変だったのでは。
小高かなり悩みましたね。ゲームに慣れている方とそうじゃない方で、まったく評価がわかれるキャラクターとかもいたので……。どちらのニーズも満たせるように、いろいろな視点から調整をしていきました。
――主人公の澄野とかはかなりオールマイティで使いやすいキャラクターですよね。
小高そうですね。テストプレイ時には澄野だけを育成しているような人もいました。性能的にも「こいつさえいればなんとかなる」という感じのポジションですね。

――お話にもありましたが、本作はキャラクターの育成要素もかなり面白いですよね。クラスメイトとの交流が主軸になっていたりして。
小高クラスメイトとの“学究活動”を通じて強化段階が解放されていくシステムですね。メディア・ビジョンさんからご提案をいただいたものだったんですが、これもクオリティアップがかなり遅くて……昨年の秋ごろぐらいに見たときはかなりひどい状況でした。プレイしても、なんの感情も沸いてこないような(笑)。
それを見たアトラス出身の登川とかが「これはまずい」と急遽手を入れてくれて。ライターの方に専用のセリフを用意してもらったり、成長のバランスとかもしっかり見極めてもらったり。もう本当に、ギリギリのタイミングで一気に進めたのを覚えていますね。
――昨年秋となるとそれこそ半年前ぐらいじゃないですか。本当にギリギリだったんですね……。
打越それこそSE(効果音)とかは去年の12月ぐらいまでまったく揃わなかったですよね。
小高そうそう。サウンドチームが死にそうになりながら作ってました。
――壮絶だ……。全体的な素材とかが揃ったタイミングってどれぐらいだったんですか?
小高今年の1月ぐらいでしょうか。そこからシナリオとかの監修もあって、だいたい作業は3月ぐらいまでやってましたね。
そもそも全体のシナリオをプレイして確認したのも、今年に入ってからなんですよ。で、やっぱり修正してほしいところとかも出てきたので、そこはもう無理やりなおしてもらいました。その時点だともうみんな麻痺していたので「よくなるならやりましょうか」という感じで。
――……なぜか隣にいる打越さんが遠い目をしていらっしゃいますが。
打越ああいや、2023年から2024年は、もう正月も大晦日もなかったなというのを思い出していまして。あのときは腱鞘炎で動かない腕をサポーターでぐるぐる巻きにして、激痛に耐えながらキーボードを叩いて……なんとか24年の頭には、100ルート全部の初稿を上げたんです。そこからスクリプトの作業に入りながら、シナリオを直したりしていきました。

小高だからこの1年ぐらいはずっと直したり、ブラッシュアップをしたりといった感じですね。
ビジュアル面もすごい大変だったんじゃないかな。先ほどもお話しましたけど、600枚ぐらいイベント絵がありますし、表情差分も1キャラにつき300個近くありますから。
――表情差分が300!?
打越似てるけど微妙に違う表情も多いんですよ。もしかしたらプレイヤーは気づかないようなものまで。
小高イラストを担当した小松崎のこだわりもありますが、ライターからの要望もあったりしてどんどん増えていきました。多分全部で3000個以上あるのかな……。でも恐らく、全表情をしっかり使っていると思います。


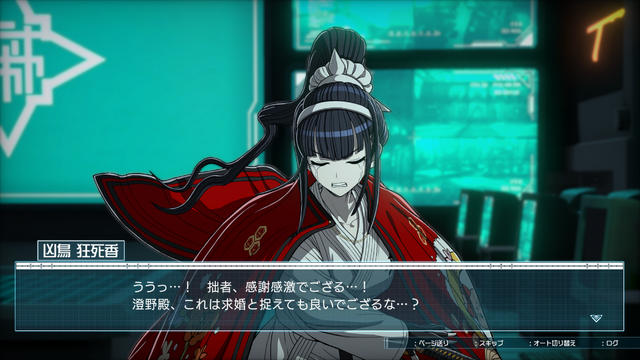
――ありがとうございます。存分に本作のこだわりというか、もはや狂気というか……そういうものを見させていただいた気分です。それでは最後に、本作を楽しみにされているファンの方々へ向けて、メッセージをお願いできますでしょうか。
小高最近はどんどんゲームがプロダクト化してきて、作品の独自性とか作り手の個性、作家性みたいなものがいらない時代になってきていると思うんです。でも僕は、その作家性みたいなものが日本のゲームが持つ良さのひとつだと思っています。
『HUNDRED LINE』のように、新規IPかつ完全な新作で、個性もあって、大手じゃ絶対に通らないような企画のゲームを大々的に出せるっていうのはあんまりないと思うんですよ。だからこそ、日本のゲームの良さを保つためにも買っていただきたいです。
打越僕としては、あんまりコンシューマーゲームをやらない層にぜひとも遊んでもらいたいですね。コンシューマーならではの、がっしりとした面白さをぜひとも体験していただきたいです。
それと、AAAタイトルとインディーゲームの中間ぐらいにいる、僕らみたいなクラスが作るゲームにも面白いものっていっぱいあるので、その取っ掛かりにもなればいいなと思います。
――ありがとうございました!
『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』は、ニンテンドースイッチ/Steam向けに2025年4月24日発売。価格は通常版が7,700円(税込)、デジタルデラックスエディション9,900円(税込)です。
またインサイドでは本作のプレイレポートも掲載中です。こちらもぜひお見逃し無く。