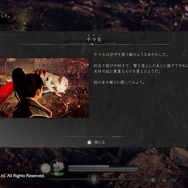高難度のダーク戦国アクションRPGとして人気のシリーズ『仁王』。最新作である『仁王3』の発売が待望されつつあり、いよいよ開幕した東京ゲームショウ2025でも試遊が展示されますが、会期前にプロデューサー陣にインタビューする機会を得ました。
答えていただいたのは『仁王』を始めとするTeam NINJAの作品を多く手掛けてきた、本作のゼネラルプロデューサー・安田文彦氏と、『仁王2』のDLCからプロデューサーを務める柴田剛平氏です。

――本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、オープンフィールドとはどういう意味でしょうか? オープンワールドという言葉を使わない理由はなんでしょうか?
安田Team NINJAで手掛けた『Rise of the Ronin』では、幕末の日本をプレイヤーとして体験してもらうという思いを込めてオープンワールドという呼称を使っていましたが、『仁王3』は戦乱の中を往くステージが多いんです。戦場を踏破してもらって、敵を討伐していく感じです。
戦国の街を描くのではなく、戦場を描いており、そのスケール感やプレイフィールはやはり異なります。そのため、より作品のイメージが誤解がなく伝わるようにメディアの方と話すときはオープンフィールドという言葉を使っています。

――シリーズも三作目となりましたが『仁王』の最大の特長はなんでしょうか?
安田プレイヤーが全力を尽くして敵に打ち勝っていくというところでしょう。難所や妖怪、有名な武将などを突破するのが特長です。
そのために多くの要素があり、攻略法もたくさん用意しています。アクションを頑張ってもいいし、フィールドを回って装備品を集めてもいいし、オンラインを使って助けてもらってもいいし、そういう多彩さも『仁王』の魅力ではないでしょうか。この点については三作目でも伸張させています。
――その特長は今回どのような形で活かされていますか?
安田攻略の自由度がより極まっています。今回は軸がふたつあって、ひとつがオープンフィールド。これまではリニアなステージ攻略のゲームでしたが、どんなルートやどんな順番で攻略していくかによってゲーム体験が大きく変わってきます。
そしてもうひとつが、アクションです。主にニンジャスタイルですね。より立体的かつスピーディーな戦いを入れたことで、アクションの自由度や多彩さが格段に増しています。

――作中で描かれる時代は、戦国時代のなかでもだいぶ後期に差し掛かってきたかと思います。前作、前々作と比べて、ストーリーにはどういった特徴があるのでしょうか?
柴田今回は「時代を超える」という特徴があって、主人公の竹千代が時代を超える力を持っています。
竹千代は自分が将軍に就任する直前に、弟の国松に裏切られて、その座を引きずり降ろされてしまうんです。そこから時代を巡って自分の処遇を変えていくというのが本作のストーリーです。
過去作では戦国時代を部分的に体験する形で、歴史上の大きな事件の中で活躍するという話だったんですが、今回は色々な時代を超えて、自分の目的を果たしていくという物語になっています。
――試遊でも1190年の平安時代を遊べるマップがありました。今のお話を聞いて『仁王2』のDLC「平安京討魔伝」を思い出しましたが、今回は自分のために時代を超えるという形なんですね。
安田あの時はソハヤマルという武器の話が縦軸でしたが、今回は将軍を巡る話なので、その点が異なりますね。
――試遊のマップは雪国でしたが、そのほかにどんなマップが存在するのでしょうか?
柴田体験版で出したのは戦国時代のマップでしたが、最後に地獄が出てきて、そこをクリアしたあとはさらにフィールドが広がっているんです。そこでまた複数のミッションが提示されて、ボスに挑んだり、深い森や敵の城に行ったりできます。
どうして平安時代の京都があんなに雪だらけになっているかというと、あれは地獄の影響を受けているんですね。つまり、時代ごとにテーマとなる地獄が異なるわけです。
戦国時代は灼熱地獄で、平安時代は極寒地獄で……といった感じで、それぞれに地獄があるんです。製品版ではそうした違いをお楽しみいただければ幸いです。

――『仁王』シリーズに元々あった要素を継いでいたり、他のアクションゲームに登場する要素と組み合わせたりと、かなりチャレンジングなことをしているかと思います。これだけ沢山の要素を入れ込んでおきながらゲームとしてまとまっているのはどういった工夫があるのでしょうか?
安田まとまってるという前提の質問で、ありがたい限りです(笑)。
たしかに要素は多いです。『仁王』の時点で構えや残心があり、それから『仁王2』で半妖になって、『仁王3』ではニンジャスタイルやオープンフィールドを採用しています。工夫と言われるとなんだか難しいんですが。
ただ『仁王』シリーズの遊びと、オープンフィールドの相性が良かったと思います。今まではリニアなステージ構成で、プレイヤーはずっと同じベクトルでキャラクターを強化していくという状況がどうしても生まれてしまっていました。しかし本作でオープンフィールドを採用したことで「ちょっとあのボスには勝てないから違う方に行ってみよう」となってくれるのではないかと思っています。
例えば、強いボスに勝てなくても、別の場所に行ったら今度は氷属性の武器が手に入ったりとか……そうなってくるとプレイヤーのほうでも氷属性の武器を使ってみようかなと思うでしょう。そして、そういった具合に多彩な攻略やビルドを試してもらっているうちに、線形的にレベルは上がっていくわけで、リニアではなく要素が散りばめられているからこそ取っつきやすく、遊びの幅も広がっているのではないかなと思いますね。

とはいえ、「俺はこれで行く!」というビルドを見つけたら、それ一本でクリアできるようにもなっているので、そういう意味でも色々と楽しんでもらえたらと思います。
柴田アクションのシステム面で言うと、サムライとニンジャのスタイルで行こうと決まった際に、攻撃手段を始めとする要素をすべて仕分けてみたんですね。その結果として、それぞれのスタイルの方針が絞れたのが大きかったです。
安田まあ、過去作にはサムライとは言いきれないような装備もいっぱいあったので……鎖鎌とか(笑)。
――社で組み替えるビルドと、メニュー画面で変えられるものなど、それぞれに細かく異なりますが、これらはどういった軸を元に決定していったのでしょうか?
安田まず、ゲームをいくつかのレイヤーで分けた際に、アクションゲームとして、接敵した瞬間にどういった動きをするのか、反射神経に訴える部分というのが、一番小さい単位として存在します。
で、次に大きい単位が「構えを変える」のように、プレイヤーがリアルタイムに操作するけど反射神経を使うほどじゃないものがあります。
さらに大きくなると、装備品やレベル上げという、バトル外のものになっていきますね。メニューを開いてゆっくり考えることです。もちろん上手い人はこれらをすべて戦いながら行えるかもしれません。
今回はニンジャスタイルなども増えているので、幅がありすぎて逆に混乱を招いてしまう恐れもあるので、ある程度こちらで整理して誘導することが必要なのかなと考えました。
そもそも社を眺めるときって落命したあとですから、そこで「今度は戦略を変えてみようかな」と思ってもらおうと、そういう軸で作っています。

――ハック&スラッシュ的な遊びも本作の醍醐味のひとつかと思います。本作にも新たなビルドや付帯効果があるのでしょうか。
柴田はい。もちろん追加しています。
サムライ・ニンジャとスタイルを分けたことで、それぞれに細かくビルドが作れるようになりました。たとえば、サムライだったら新しい「技研ぎ」というアクションがありますが、これを強くする効果をもった装備のスキルがあります。
逆にニンジャだったら「忍術」を強くする装備の揃え効果があったりだとか、そういった具合にそれぞれに新しい効果を追加しています。
――アイテムや装備品のドロップ率などについてはどういった指標で作っているのでしょうか。
柴田色々な指標があるのですが、大きなファクターのひとつはプレイの体感時間です。たとえば、1時間プレイしたら何個入手できるか……といった感じですね。他には、ゲーム進行にあわせて、飽きが来ないように新しいものがドロップするような調整をしています。
それと、これは今までのシリーズにもありますが、今持っている武器と同じ種類のものが落ちやすくなっているので、ビルドは組みやすいかと思います。もちろん偏らないように他のものも落ちてきますのでご安心ください。

――今回もたくさんの妖怪が出てくるようで楽しみです。お二人が好きな新しい妖怪と、お気に入りの妖怪を教えてください。
柴田私が好きなのは新しいマスコットの千々古(ちぢこ)ですね。空を飛んでいる鈴の付いたイタチの妖怪なんですが、こいつに的当て遊びをすると改変武技が手に入ります。可愛さもありますが、フィールド探索中に鈴の音が聞こえたら「おっ、強化できる」と嬉しくなれるので好きです。
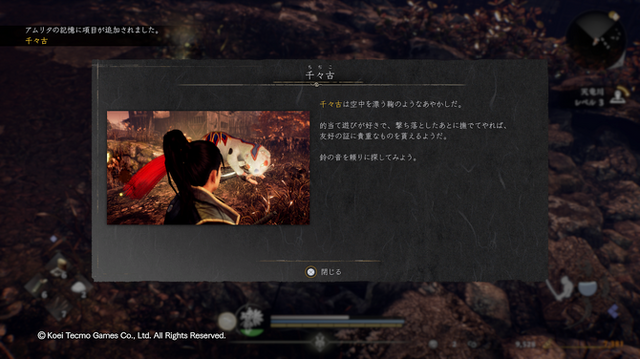
安田私は『仁王2』から続投のすねこすりがオープンフィールドを自由に駆け回っているのを見れて嬉しかったですね。シリーズの進化として、すねこすりはシリーズファンの皆さんにも喜んでもらえると思います。
また、これも『仁王2』からいる餓鬼(がき)というザコ敵がいるんですが、これの大きい個体として“餓鬼大将”というのが追加されました。聞いたときに「天才的なネーミングセンスだ」と感動しました(笑)。
――開発中、もっとも苦労した点や、やってよかったことなどを教えてください。
柴田苦労したのはやはり新しい要素をどうシリーズの良さに落とし込むかですね。サムライ・ニンジャのバランスを壊さないこと、そして『仁王』らしさとオープンフィールドの両立も考えました。
オープンフィールドも広くしすぎたり、狭くしすぎたりを繰り返しつつ、遊びながら「これは『仁王』らしいよね」といえるプレイフィールを目指して開発を続けています。最初は「釣りとか入れる?」とか言ってましたから。死にゲーに釣りは求められてないということでオミットしました……(笑)。
あとは、体験版を作ってフィードバックを得られたのも大きかったですね。ご好評いただけたのも幸いでした。
安田今作は発表と体験版の配信が同時だったんですよね。そこも良かったのかなと思っています。発表だけだと「制作中なんだ」で終わってしまいますけど、触れるものがあったほうがいいなと。今作は前作から(現時点で)5年くらい空いてますから、そういう意味でも早い段階でプレイヤーの直接的なフィードバックを得られたのは良かったです。

――今回の試遊では、武田信玄が何の説明もなく化物として出てきたのも面白かったポイントでした。コーエーテクモゲームスさんの伝統というか、歴史を自由に解釈しているところが素敵だなと感じております。
安田たしかに「武田信玄と戦うと聞いていたけど話が違う!」ってなりますよね(笑)。TGSの会場にもとんでもなくデカい信玄がいるのでぜひコーエーテクモブースに見に来てください。

――『仁王2』でも秀吉の描き方など、日本史の面白いところを突いているなと思っていました。
安田やはり歴史の謎やミステリーを話の軸にしたいとは毎回思っています。
柴田ちなみに今回は「時代を超える」という要素があるので、シリーズ作の中では最も我々の創作部分が多いです。とはいえ、その時代ごとに有名な史実のエピソードと絡んでいくので、歴史ファンにも楽しんでもらえるのではないでしょうか。
――今後の『仁王』シリーズやTeam NINJAの展開において、挑戦してみたいことがあれば教えてください。
柴田まずは『仁王3』を発売することが第一ですが、もしも好評をいただけたら、世界観を活かした別の角度のゲームをやってみたいと、個人的には思います。
安田3人で協力して強力なボスに挑むようなゲームですか?……『仁王3』が1000万本以上売れたら検討しましょう(笑)。

――とても楽しみにしています(笑)。
柴田それはそうと、和のダークファンタジーは好きですし、妖怪や武器・鎧の類は他のコンテンツでも応用が利くし、深掘りできるものだと思ってるので、これらを使って何かできないかなとは思っています。
安田Team NINJAとしては『Rise of the Ronin』がなかったら『仁王』をオープンフィールドにしなかったでしょうし、今後もオープンワールドやオープンフィールドには挑戦したいと思っています。
そして、違うジャンルも作りたいです。我々のコンテンツに対してユーザーは完全に新しいものを求めているわけではないと思うので、何らかの軸は置きつつも、新しいチャレンジに少しずつ取り組んでいければと考えています。
シリーズの柱となるデザインからストーリーテリング、そしてゲーム設計に至るまで、縦横無尽に答えていただいたインタビューとなりました。シリーズ三作目にしてオープンフィールド化し、さらなる完成度を誇った『仁王3』……発売が楽しみです!
『仁王3』は2026年2月6日、SteamとPlayStation 5にて発売予定です。
¥16,280
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
¥16,280
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)