 |
| 新妻プロデューサー(左)、川田プロデューサー(右) |
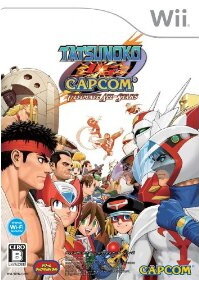 | 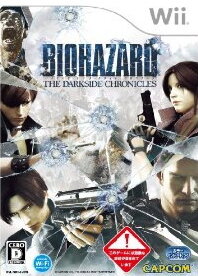 |
| 新妻氏の手がける『TATSUNOKO VS. CAPCOM ULTIMATE ALL-STARS』 | 川田氏の手がける『バイオハザード/ダークサイド・クロニクルズ』 |
―――お二人は席が近いというお話でしたが(前編を参照)、お互いに仕事ぶりを見ていて、参考にされることはありますか?
川田:そうですね。もっと立ち入る必要があるのかな、と思っているんです。実は最近、稲船(*)に叱られまして。おまえらしっかり情報共有できているのかと。
(*)稲船敬二……カプコンの開発部門のトップ。『デッドライジング』『ロストプラネット』などを手がけたプロデューサーとして有名。
新妻:おまえら横を見てないって。それは会社的にも上から言われていることなんですよ。
―――ではプロデューサーとして、気をつけていらっしゃることは?
新妻:さっきも言いましたが、僕は神経質な方で、何でも割と理詰めで進める方なんです。だから部下を叱るときも、つい理詰めで叱ってしまうんですよ。だから叱られる方も逃げ場がなくなってしまう。
―――わかります。
新妻:それに比べて川田Pはうまいんですよ。たとえば机の脇で話をしていて、エキサイトしてくると、後は会議室で話をしようかって、すっと見えない場所に移動してしまう。みんなの前で叱ってしまうと、どうしてもつるし上げみたいになりますからね。逆に僕は電話でよく「どうするのこれ。全然できてないやん」って冷たい声で言ってしまって、電話口で向こうが何も言えなくなったりして。そのへんは川田Pを見習いたいところです。
川田:僕は早く帰れるようになりたいですね。ほんとに、早く帰れるようにしないと駄目ですよ。そうして自分の時間を作らないと外を向けない。情報も集まらないじゃないですか。もちろん仕事が適当では駄目ですし。そのためには段取りをきっちり組むとか、整理整頓をするとか、処理能力を高めていかないといけない。(笑)さっきの「ゲームを1日1時間遊ぶ」というのも、それが前提ですから。
―――ボスが帰らないと、下の者も気をつかって、帰りにくいですからね。
新妻:そうですよね。だから上も気を遣わないといけない。
―――ただ、チームを統括するのも大変でしょう。モチベーションを高める上で、何かされていることはありますか?
川田:うーん、どうだろう。ほかの会社さんと、そんなに変わらないと思いますけどね。ほめて、叱って、持ち上げて、その繰り返しというか。
―――なにかの記事で拝見したんですが、ゲームの発売日に梅田のヨドバシカメラにチームで行って、お客さんが自分たちのゲームを買う姿を観察する習慣があるそうですね。
川田:あれっ、それって、みんなやってないんですか?
―――業務用ならまだしも、家庭用では珍しいですね。自分が手がけたゲームを、お客さんが買う姿を見たことがない開発者って、意外と多いと思います。
 |
| 新妻氏(左)、川田氏(右) |
新妻:僕も割と意識的に見ています。というのも、ゲーム作りのゴール地点はマスターアップじゃなくて、お客さんに届いてゴールなので。だからちゃんと届いてるかも見たいし、良い意見も悪い意見も全部聞いた上でゴールと思ってるので、それを全部飲みこんで次のスタートに備えるのが仕事だから、作って終わってすぐアップ休みというのはちょっと違うのかなと。だからそこまで責任を持つというのが普通かなと思ってました。
―――そういった習慣は業界で広めていきたいですね。
新妻:そういえば『バイオハザード5』でスタッフが百数十人もいるのに、クリスマスに全員分のケーキとフライドチキンを用意されたことがありましたよね。それも川田Pと竹内Pの自腹で(笑)。
川田:そうなんですよ。竹内が「こいつらにはクリスマスがない。年末年始もない。何か報いないとダメだろう」と言い出して。たまたま僕はその日に買い物をしようと思って、幾ばくかのお金を財布に入れていたんですが、それがさーっと消えてしまいました。(笑)
新妻:あれ十万円近くとかでしたよね(笑)。
川田:ディレクターもけっこう無茶してるんですよね。万単位でみんなにご飯をおごっていたりして。体育会系のノリの延長ですよ。しまいには、プロデューサーって現場におごってナンボですよね、みたいな奴らまで出てきたり。おいおいって。(笑)
新妻:でも、ふざけていても、ネタでもいいんで、そういうことが言える距離感って大事じゃないですか。「プロデューサー様」ではなくて、「ちょっとおごってくださいよー」「なんでおまえにおごらなあかんねん(笑)」って言える、ノリと距離の近さがあるからこそ、活気が出てくる。お互いに「全然理解してくれてない!」「そんなん知るかー」なんて言い合いがあったとしても、その後ですっきりして飯食いましょう、飲みに行きましょうーで終わるし。でも距離感が遠いと、お互いに言いたいことが言えなかったりして、ため込んだりしますからね。
―――そうですね。
川田:そういえば『バイオハザード5』を作っていたとき、竹内と僕とグラフィックのチーフでミーティングをしていて、大喧嘩になったんですよ。お互い、すごい剣幕で怒鳴り立てて。机をバーンと叩いたりするんです。それを見て、僕は不覚にも笑ってしまったんですよ。(笑)うちの会社って、まだこんなことができるんだなと。お互い、いい年なんですけどね。30代半ばを過ぎて、仕事でこんなに真剣に怒鳴りあえるんだというのが、嬉しかったですね。
―――そういう喧々諤々の議論というのは今回お二人のタイトルでもあったのですか?
川田:そうですね……。「ダークサイド」では、ヒロインでマニエラという新キャラクターが出てくるんです。そのキャラクターデザインは苦労しました。
―――というと?
川田:南米が舞台のシナリオに出てくるキャラクターで、かわいらしくしたいというディレクターの意図もありまして、南国的で、かつ華奢なイメージで考えていたんです。でも最初にあがってきたゲームのモデルを見たら、対戦格闘のキャラみたいな、ごついお姉ちゃんで。おいおい、これは違うんじゃないかと。
―――ははは。
川田:ただキャラクターデザイナーとしては、打ち合わせのイメージを元に、自分なりの解釈も加えて、ベストなものを作ってきているんですよね。でも、どう考えても、ゲーム中でこの、ごつい姉ちゃんを守りたいとは思わないよね、という話をして。コミュニケーションがしっかりできていない失敗例で反省しています。同じ新キャラクターでも悪役のハヴィエなど、イメージがはっきりしている場合は、すんなりとできたのですが。なかなかヒロインとなると作り手の思惑も厳しくなるようで。(笑)
 |  |  |
| 『バイオハザード/ダークサイド・クロニクルズ』は好評発売中 | ||
―――作り手の、みんなの思いがスパークするところですよね。
川田:ええ。作り手として、一番力を入れるところですので、ぜひ皆さんにも見ていただければ。
新妻:『タツカプUAS』では、方向性ではそんなに喧々諤々はないんですが、どこまでどの要素を入れるかの割合で言い合いにはなりますね。キャラに愛がある分、譲れないところがみんなバラバラで(笑)。そんなメンバーをなだめる為、声優さんのボイス録音に連れてったりしたんですが、コンドルのジョー役では、ささきいさおさんにスタジオに来ていただいたんです。さすがにそのときはオーラが違いましたね。僕らの作るモノに、ささきさんが声をアテてくれるんだぜって。現場のメンバーもすごく喜んで、だったら声に負けないように格好いいモノを作ろうって、いい方向でメンバーが納得して修正ができたりしましたね。
川田:あとはIGN.com(アメリカの大手ゲーム情報サイト)で、『タツカプUAS』が「ベスト・ファイティングゲーム」賞を取ったときも、アメリカ人のマーケティングスタッフの喜びようはなかったですね。賞を取ったからには盛り上げないと、という感じでプロモーションも増えていきましたし、マーケティングも行ったりして。特に仕事に対するポジティブな姿勢は見習わないといけないですね。稲船にも言われるんですよ。「おまえらはネガティブすぎる」って。(苦笑)
 |  |  |
| 海外でも注目を集める『タツカプUAS』 | ||
―――では最後に、今年作りたいゲームについて教えてください。こういったものに挑戦してみたい、という抱負でもかまいません。
川田:僕は血液型がAB型で、好みも両極端なんですよね。今までホラー系のゲームが多かったので、先に言った「レイトン教授」みたいなものもいいなと。誰もが手に取りやすいタイトルって憧れですね。CERO D(17歳以上対象)のタイトルが多かったので、CERO A(全年齢対象)のタイトルも作りたいですね。うちの「逆転裁判」シリーズの担当者とか、ものすごくうらやましいですよ。
―――そうなんですか。
 |
新妻:僕も同じような話で申し訳ないんですが、今まで対戦格闘ゲームばかりでしたが、個人的には、シミュレーションゲームが大好きなんですよ。それこそチュートリアルだけで2時間くらいかかるゲームを、ニヤニヤしながら遊んだりして。だからそういうのにもあこがれます。
―――それもまた意外でした。
新妻:あとは昔好きだったジャンルがパズルゲームなんです。『IQ』『Xai』などは、ずーっと遊んでいました。だからほんとにカプコンらしからぬ、ライトなイメージで、アイディア勝負のゲームを作ってみたいですね。
―――ではホントに最後に、今年の抱負を一言ずつ。
川田:早く帰るぞと。(笑)いや、こんな抱負じゃいけないですよね。今年はいろいろ仕込みが必要な年になりそうですので、はやく形になるようにがんばります。
新妻:僕はかっちりしすぎなので、もうちょっと余裕をもって取り組みたいですね。その中で良い結果を出していきたいなと思います。
川田:ただ二人とも共通するのは、今年も面白いゲームを作りたいってことですね。何が面白いのかは人によって違うと思いますが、まず自分がおもしろいと思えるゲームを作って、それで最終的にユーザーの皆さんに喜んでもらえるものになればいいと思っています。
新妻:ちなみに土本さんの今年の目標は何ですか?
―――僕ですか? インサイドを日本一のゲーム媒体にすることです。
川田:そういう心意気って、やっぱり重要ですしすばらしいですね。
 |
―――今日は長時間、ホントにありがとうございました。

















