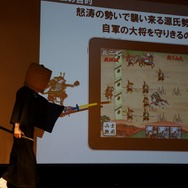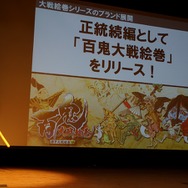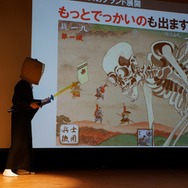『セガカラ』と『源平大戦絵巻』の開発者が示す、ソーシャルメディア時代におけるユーザーとの関わり方・・・中村彰憲「ゲームビジネス新潮流」第24回
ソーシャルメディア全盛の時代と言われますが、ゲーム開発者はユーザーとどのように接していけば良いのでしょうか? セガの3名の開発者が自身の経験を明らかにします。
ゲームビジネス
開発

冒頭は、デュラ氏と新小田氏が『大戦絵巻』シリーズの開発秘話を披露。2011年6月2日にリリースされた『源平大戦絵巻』(以下、『源平』)を皮切りに、『アレクサンドリア大戦絵巻』(以下、『アレクサンドリア』)、『百鬼大戦絵巻』(以下、『百鬼』)と既に3作品がリリースされています。これらの作品における共通点は、プレイヤーが指揮官となり、複数カードで部隊を編成。iPadを絵巻物に見立て、自軍の大将に向かってくる敵を殲滅していくという点。グラフィックは、当時の絵巻物や、パピルスのデザインをそのままモチーフにし、まるで「動く絵巻物」といった感があるのがこのシリーズの特徴です。
2011年6月に発売された『源平』は、同年9月には『Samurai Bloodshow』として全世界に配信開始。現在、日本語、英語に加え、韓国語、中国語、フランス語、スペイン語等、全6カ国語で展開。これまで30万ダウンロードを突破したとのこと。また海外各国のゲームレビューサイトでもそのゲーム性が高く評価されているとのことです。
ここで、デュラ氏が海外向けタイトルの命名エピソードについて語りました。「Bloodshow」(血のショウ)とは、敵を倒すと血しぶきしたたる『大戦絵巻』シリーズとしては如何にも、といった響きですが、「きっかけは実は全然ちがう」とデュラ氏。「その当時、作り始めの頃はやっていたTVドラマ「Sex and the City」の主人公がCarrie Bradshawだと知ったとき、コレだっ!とひらめいたんです」(同氏)。
このように、推敲に推敲を重ね、考え倒すだけでなく、脱力して考えたときにいいアイデアが出る場合もあるとし、アイデアが如何に多様な形で出てくるのかを示しました。
ゲームを開発するにあたり、考えたのが日本としての強みを生かす事。そこで、他国でも扱われるであろうSFやファンタジーなどではなく、日本の歴史をゲームの題材にしたとのこと。
更に音楽にもこだわったとデュラ氏。日本の代表的な和楽器である琵琶を使用したのに加え、テクノを入れるなどして、ネオジャポニズムをテーマとして作ったとのこと。この音楽が好評で、iTune Music Storeで楽曲を配信したところ、全サントラアルバム部門ランキングで第1位を獲得しています。
一方、2作目である『アレクサンドリア』では、世界二大文明である、エジプトと、ギリシャをぶつけたいという思いから開発したとデュラ氏。アレクサンドリアはこの二大文明の分岐点というところでタイトルも決定しました。また、『源平』の正当続編にあたる『百鬼』は、従来の源平というテーマに妖怪を大量に追加。これらの妖怪デザインは、「百鬼夜行絵巻」をベースに、歌河国芳や、河鍋暁斎などの妖怪絵師が描いた魑魅魍魎を取り入れているとのことです。
■ゲームバランスを洗練させ「脳汁が出る」体験を保証する
《中村彰憲》
この記事の写真
/