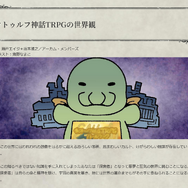2025年10月23日、『Lair of the Leviathan』を制作している海外ゲーム制作グループNostalgic RealmsのDavid氏は、「日本では『クトゥルフ神話TRPG』が最も人気のあるロールプレイシステムになっている理由にとても興味があります。 やはり世界観が理由なのでしょうか?」という日本語のポストをX(旧Twitter)にて行いました。
『クトゥルフ神話TRPG』が日本で最大規模のTRPGの理由、有力なのは「ニコニコ動画」と「這いよれ!ニャル子さん」の影響

『クトゥルフ神話TRPG』(旧題:『クトゥルフの呼び声(Call of Cthulhu)』)は、1981年よりケイオシアム社から発売され、現在も最新は第7版として刊行が続いているTRPGです。そして、2025年の現代日本で間違いなくトップシェアのTRPGでもあります。
『クトゥルフの呼び声』という旧題があることが示す通り、このTRPG自体は1980年代から和訳されていましたが、その頃はファンタジーブーム真っただ中。日本では、入手性やメディア展開なども相まって人気となった『ソード・ワールドRPG』などの作品に押されていて、トップシェアのTRPGというわけではありませんでした。

しかしながら、「クトゥルフ・ハンドブック」などの著書があるSF作家の山本弘氏や、1992年にクトゥルフ神話の代表作「インスマスを覆う影」を日本を舞台に翻案したドラマを手がけた俳優の佐野史郎氏など、当時からクトゥルフ神話の愛好家は少なくなく、また『クトゥルフ神話TRPG』の世界観や各種スキルなどは現代日本に置き換えることも可能なことから、剣と魔法のファンタジーでない「現代モノ」で遊びたいTRPGプレイヤーからは『クトゥルフ神話TRPG』は重宝されました。
転機が訪れたのは2010年代のニコニコ動画の隆盛です。ここで『クトゥルフ神話TRPG』を題材にしたリプレイ動画の人気が一気に高まり、TRPG未プレイ者にもわかりやすいシステムとしてTRPG未プレイ層にも一気に広がりを見せました。

また、2010年代のニコニコ動画が人気を博していたのと同時期に、クトゥルフ神話を「美少女が登場するライトノベル」として再解釈した「這いよれ!ニャル子さん」や、初出はアダルトゲームながらスーパーロボットものとしてクトゥルフ神話を再解釈した『斬魔大聖デモンベイン』が人気を獲得したのも『クトゥルフ神話TRPG』の人気の隆盛に一役買ったといえるでしょう。
この辺りの日本での盛り上がりの解説については、クトゥルー神話研究家として知られる森瀬繚氏への電ファミニコゲーマーのインタビュー記事が非常に詳しいので、こちらも参考にしてください。
冒頭のDavid氏の質問に戻りますと、氏は「日本国内で発売された、海外ではあまり知られていないビデオゲームなどはありますか?」という質問もしています。

『クトゥルフ神話TRPG』のルールをそのまま用いたゲームではありませんが、日本発のビデオゲームとして「クトゥルフもの」として有名なのは1987年の『ラプラスの魔』で、MPを失うと発狂してしまうなど、『クトゥルフ神話TRPG』を強く意識したルール設定がなされています。また、本作の小説版は先述した山本弘氏によって書かれており、よりクトゥルフ神話を意識した小説に仕上がっています。
世界観のフレーバーとしてクトゥルフ神話をゲームの世界設定に組み入れたゲームと言えば、先述した『斬魔大聖デモンベイン』などが有名ですが、マイナーなところだと『ウィザードリィオンライン』をはじめとする「ウィザードリィルネサンス」期のゲームの背景設定にもクトゥルフ神話が組み込まれていました。『ウィザードリィオンライン』のダンジョンにはクトゥルフ神話作品でお馴染みの「ミスカトニック大学」がありましたし、『ウィザードリィ 生命の楔』には「ク=リトル・リトル」「ドール」などのクトゥルフ・モンスターが登場します。
もっとマイナーなところを突くと、それまでのシリーズ作品とは全く無関係の作品となった『エルミナージュ ゴシック』には「ロスルリエ遺跡」(R'lyeh、すなわち「ルルイエ」)や、「クスグァ(クトゥグア)」「ツァール」「サイクラノス(サイクラノーシュ)」といったクトゥルフ神話の地名・神族たちが数多く引用されています。
その他、『真・女神転生』『ペルソナ』シリーズや『ドラゴンポーカー』をはじめとするスマートフォンゲームなど、クトゥルフ神話をフレーバーとして活用しているゲームは挙げればキリがありません。それだけ、クトゥルフ神話は現代において広く伝播したといえるでしょう。
皆様にも「ゲームとクトゥルフ神話」に関する思い入れや意見はありますか?是非ともコメント欄でお伝えください。